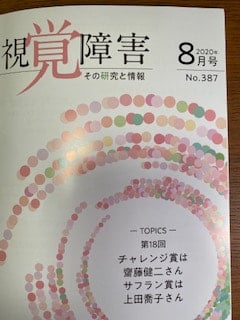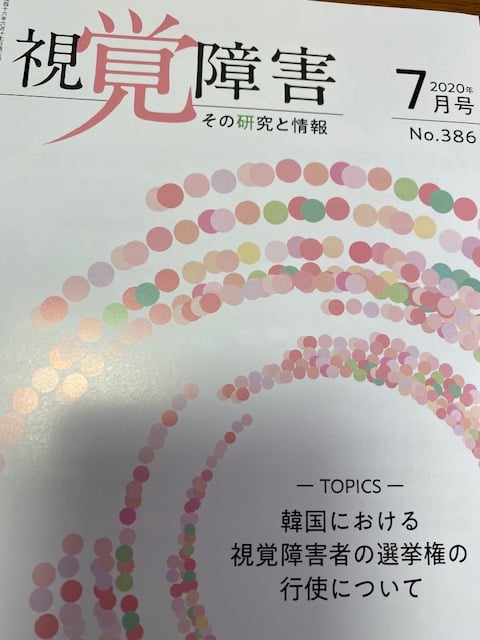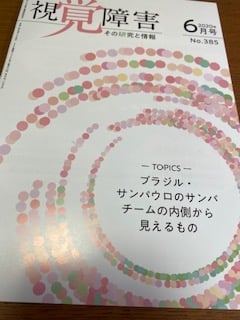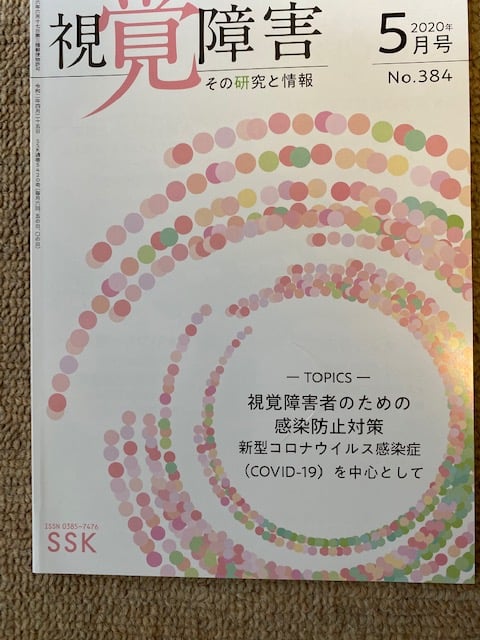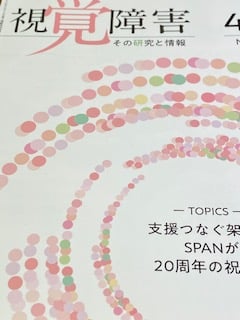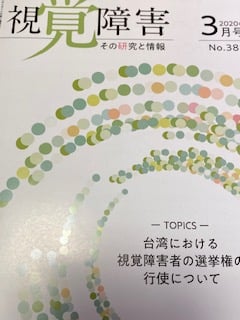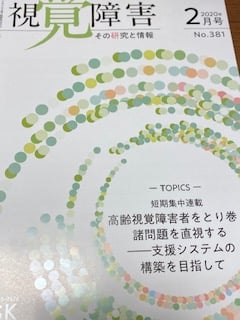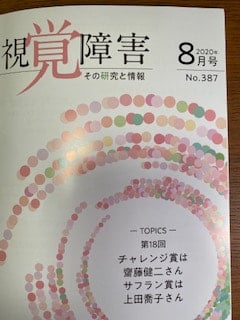 月刊視覚障害8月号表紙
月刊視覚障害8月号表紙
コロナ禍の中、猛暑も続いていて暑い暑いと言っている内に、あっという間に1ヶ月が過ぎてしまいました。
「高齢視覚障害者を取り巻く問題を直視する」の連載も7回目になり、私が思っているよりも、多くの方に読んでいただいているようで、高齢視覚障害者の状況や、その支援に取り組む方達のことを、少しでも多くの方に知って欲しいと思い、頑張って書いています。本当なら、現場に取材に行きたいし、直に皆さんのお話を聞きたいのですが、今は無理。そんな中ですが、オンラインでのインタビューにも、皆さんとても協力してくださって、沢山資料を出してくださって、私もすごく勉強になっています。本当に感謝しています。
さて、7月号のアイさんの記事は、沢山の高齢視覚障害者の方に勇気を与えたみたいです。良かったです。今回は、アイさんを実際に支援してくださった側の方達の思いを書かせていただきました。読んでいただければ幸いです。
「高齢視覚障害者を取り巻く問題を直視する」の連載3回目で取り上げた、私の通っているデイサービス施設エバーウォーク両国店での、施設管理責任者や職員の皆さんと話し合って、見えにくい私にでも掲示物等が見やすくなった環境改善の経過について、「視覚障害者のいろいろを一般の方達に知って欲しい」という目的で、ウエブメディアに記事を載せているSpotliteにお願いして現地取材をしていただきました。その記事が、2回に分けて公開されたので、興味のある方は、見てください。軽妙な文章と写真入りで、なかなか分かりやすい記事になっています。
第1回 ロービジョンの利用者に配慮したデイサービス施設。具体的な工夫と想定外の良い影響とは?
第2回 地域での高齢視覚リハの在り方を考える~デイサービス施設管理者とロービジョン当事者のインタビューから~
なお、Spotliteの記事には、興味深い記事がいろいろとありますので、ちょっとのぞいて見ることをおすすめします。
Spotliteトップページ
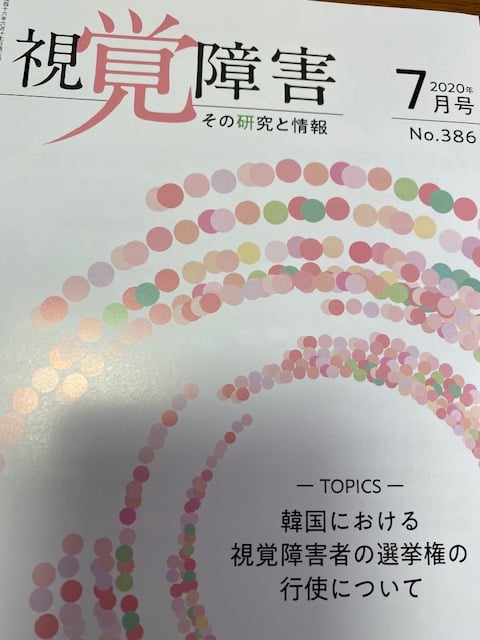 月刊視覚障害7月号表紙
月刊視覚障害7月号表紙
1ヶ月なんてあっという間に過ぎてしまいますね。「高齢視覚障害者を取り巻く問題を直視する」の連載も7月号で6回目になりました。世の中、新型コロナウィルスの感染拡大は収まらず、九州や東北地方では、豪雨災害が起こり、本当に不安で先の見えない事態になっています。そんな中、この連載がどのぐらい意味を持つのか、時々そんなことを考えてしまいます。しかし、世の中の状況が苦しいからこそ、そんな中で、奮闘している方達のことを、書いて行きたいと思っています。
今回は、高齢になって、見えにくくなった方が、機能訓練施設に入所されて、そこで、自分なりの生き方を維持するために頑張ってこられた記録です。人間いくつになっても、発達するという可能性を確信させていただいた力強い記録です。読んで見てください。
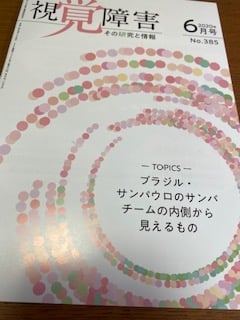 月刊視覚障害5月号の表紙
月刊視覚障害5月号の表紙
本当に月日の建つのは早いですね。明日から7月です。そしてジメジメとした梅雨シーズン。コロナウイルスがジメジメに弱いと良いのですが、東京都の感染者数は少しずつ上昇していて、梅雨だから、夏だからウイルスの勢力が衰えるという明確な証拠はないようです。私も高齢者、介護保険のデイサービス施設に通所している身なので、人に感染させない、私も感染しないという覚悟で、自衛している毎日です。
さて、今日私の手元に「月刊視覚障害7月号」が届きましたので、いつものお約束で6月号の内容をアップします。梅雨時で気分爽やかと言う訳にいかない中、取り上げている話題は、少し理屈っぽい話ですが、「なぜ視覚リハは我が国の制度の中にきちんと位置づけられていないのか」について、私なりに意見を書かせていただきました。読んでいただいて、ご意見など聞かせていただければ幸いです。
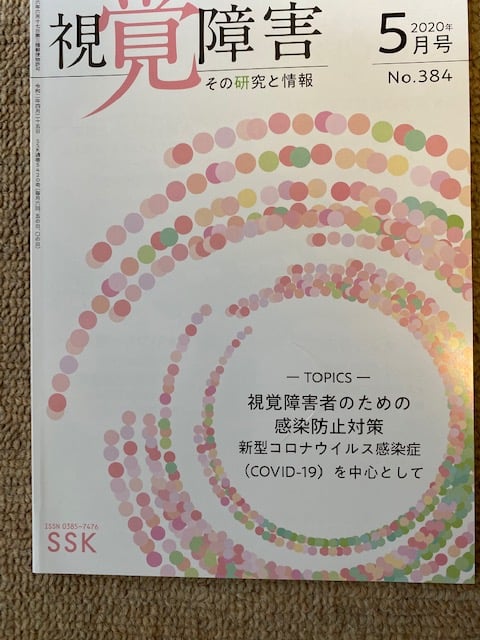 「月刊視覚障害」2020年5月号表紙
「月刊視覚障害」2020年5月号表紙
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための緊急事態宣言、東京などに出されていたものも5月25日の夜に解除されました。けれども、まだまだホット気を抜けないなと思っています。皆さんはいかがでしょうか。
さて、1ヶ月なんて本当にあっという間ですね。月刊視覚障害の6月号が今日私の手元に届きました。それで、いつものルールに従って、1ヶ月前に発行された5月号に掲載した「高齢視覚障害者を取り巻く問題を直視する」の連載4回目をこのブログで公開します。読んでいただければ幸いです。
今年は猛暑になりそうだとのこと、マスクをつけていると熱中症になりやすいとも聞いています。ストレスフルな環境の中、皆さんお体を大切に過ごしましょう。
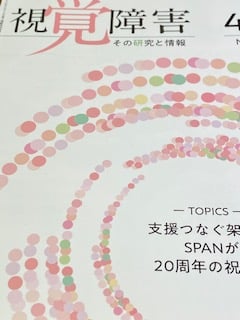 月刊視覚障害4月号表紙
月刊視覚障害4月号表紙
時間の建つのは早い物で、今日から5月になりました。新型コロナウイルスの感染拡大を防止するための「緊急事態宣言」が出て,早くも3週間が過ぎましたが、拡大の収束にはまだほど遠い状況。外は,気持ちよく晴れて,緑がだんだん濃くなっている絶好のシーズンですが、今はひたすら我慢して、自宅にとどまっています。だから時間が沢山あります。ちょうど原稿を書くには良いのかもしれません。さて私が連載している「月刊視覚障害」の5月号が私の手元に届き、高齢視覚リハ問題の連載も4回目に入りました。編集室との約束で、新しい雑誌が出たら、前の記事を、私のブログにアップしても良いと言うことで、4月号の内容を掲載いたします。今回は,見えにくい方達についての施設の環境改善の話です。ちょっとした工夫をすると,視覚障害者の方達だけでなく,高齢になって見えにくくなってきた方達にとっても使いやすい施設になるという話です。是非興味を持って読んでいただければ幸いです。
3月の終わりに、SPOTLITEのインタビューを受け、その記事がネット上に公開されました。とても素敵な写真と共に、私の言いたかったことを沢山言わせていただきました。興味のある方、是非見てください。
https://spot-lite.jp/yoshino-yumiko/
SPOTLITEというチームがどうしてできたのか、何を目指しているのか、そして沢山の視覚障害者のインタビュー記事を見てください。すごく面白いです。
https://spot-lite.jp/
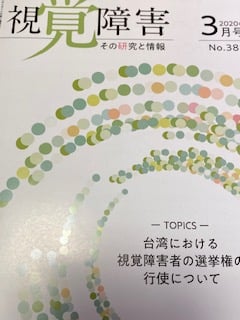 月刊視覚障害NO.382
月刊視覚障害NO.382
時間の建つのは早い物で、明日から4月になります。私が連載している「月刊視覚障害」の4月号が手元に届き、高齢視覚リハ問題の連載も3回目に入りました。編集室との約束で、新しい雑誌が出たら、前の記事を、私のブログにアップしても良いと言うことで、2月号の内容を掲載いたします。沢山の方に、高齢視覚障害者の直面する問題について、是非興味を持っていただいて、一緒に解決に向かって進んでいけたらと思っております。
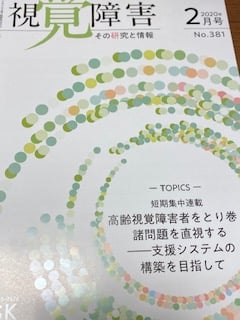 月刊視覚障害NO、381表紙
月刊視覚障害NO、381表紙
現在私の年齢は72歳、幼い頃から低身長で、脊髄側湾と大腿骨の変形という障害を視覚と共に持っている重複障害者であったが、3年ほど前に、骨粗鬆症からきたと思われる第5葉対の圧迫骨折をしてから、脊柱管狭窄症の痛みに悩まされて、長い距離を歩くのも難しくなって、今介護保険を利用して、週2回リハビリ特化型のデイサービス施設に通って、少しでも運動能力を維持したいと頑張っている。この自分の経験を通して、高齢視覚障害者の直面する問題について、自分事として深く考えて見たいという思いが強くなってきた。私なりに述べたいことを「月刊視覚障害」の編集室に持ち込んで、その企画を認めていただき、「高齢視覚障害者を取り巻く諸問題を直視する-支援システムの構築を目指して-」というタイトルで、5回ないし6回の連載をさせていただくことになった。
この記事を、雑誌が出てから1ヶ月を過ぎた後で、私のブログで公開するという許可を「月刊視覚障害」の編集室から得て、毎月、記事をの内容公開できるようになった。もし興味があったら読んで見てください。
以下雑誌に掲載した本文です。
沢山の準備をしていただき、とても良い雰囲気で話せました
 講演している私
講演している私
佐賀で視覚障害者生活訓練指導員(歩行訓練士)として頑張っておられる南さんから、「スマートサイトと地域連携の重要性」について話してくれませんかという依頼を昨年8月ぐらいに受けて、「佐賀に行くのは生まれて初めてだし、私で役に立つなら喜んで」ということで、引き受けて、2月15日に30人ほど集まった素敵な雰囲気の研修会で講師をさせていただきました。
その研修会には、眼科医、視能訓練士、盲学校の先生、当事者の方たち、県会議員、生活介護施設の職員、ホームヘルパーの方など多職種の多彩な顔ぶれの方が参加しておられて、とても良い雰囲気でした。
どうしてこんなに多職種の方たちが集まってくださったのかというと、それは南さんの準備が素晴らしかったから。会の案内チラシには、私の履歴をバッチリ、視覚リハ専門家であることとロービジョンのある当事者であることを書いてバッチリ売り込みをしてくださいました。
R2.2.15案内チラシ.pdfをダウンロード