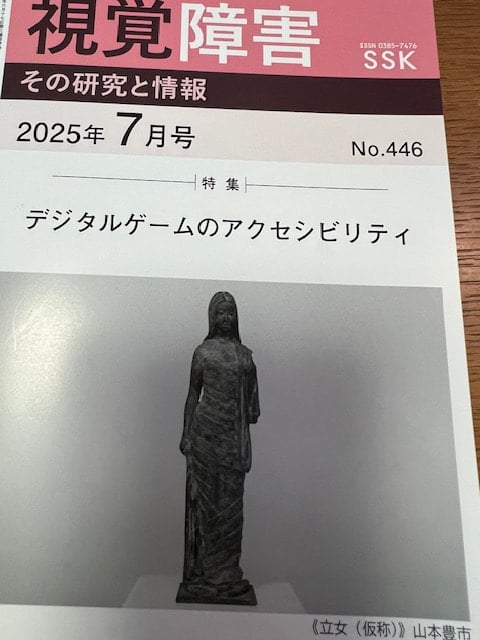
一昨年の10月ごろから、原因不明の体調不良が続き、いろいろと検査をした結果、難病の重症筋無力症ということが判明し、昨年1月に脳神経内科に緊急入院、その年の9月に、呼吸の苦しさがあり、循環器内科に相談したら、肺塞栓と診断されて、またまた緊急入院、肺塞栓の治療は、無事完了したのですが、その時の詳しいCT検査で、なんと腸間膜に動脈瘤が出来ていることが見つかって、今年の3月に、その手術で、またまた入院。一昨年から立て続きの緊急入院、自分でもびっくりでしたが、運良く、専門の先生に適切な処置をしていただき、今は、自宅でほぼ、元通りの生活をしています。すごい猛暑で、少々参っていますが。
そんな立て続けの緊急入院の体験の中で、「入院直後から始まる視覚リハの重要性」に気づき、そのことを、月刊視覚障害7月号に書かせていただきました。多くの皆さんに、この原稿を是非読んでいただきたくて、月刊視覚障害の編集部の許可を得て、私のブログに公開させていただきました。是非読んで見ていただければ幸いです。
雑誌には書けなかったけれど、書きたかったエビソード
私は、今年の3月に、見つかった動脈瘤の血流を遮断するための手術を受けるために、外科病棟の4人部屋に4日ほど入院しました。その部屋には、概ね80歳以上と思われる患者さんが入院していて、皆さん血糖値が高く、透析を受けている方も二人いらっしゃるようでした。カーテンで仕切られている部屋の様子は、聞こえてきてしまうものです。私を除く3人の方は、身体的なリハの処方が出ているらしく、毎日、リハ室に行く方、ベッドサイドでリハを受けている方がおられました。
私のベットの隣におられる方は、80歳は過ぎておられるようで、統制を受けておられて、その上に、結構大変な手術を受けられたようでした。その方のところには、ベッドサイドに多分理学療法士の方だと想像できる方が来て、「体のために少しでも起き上がって見ましょう」とか「ちょっと横向きになって見ましょうか」などと、少しでも体を動かすように、いろいろと話しかけて、励ましたりしているのです。でも、その日は、患者さんは、よほどしんどかったのか、気力が起きないのか、それは分からないですが、どうしても、ベッドから起き上がることも、体を動かすことにも応じなかったです。そんなやりとりをして、多分20分ぐらいPTの方は、少し残念そうに「今日は、疲れておられるようですし、これで行きますが、明日また来ますから、その時は、体を動かして見ましょうね、約束ですよ」などと言って、帰って行かれました。
この様子を聞きながら、疾患で見えない・見えにくい状態になって、何も出来ないと嘆いている方や、視覚障害があって他の疾患で入院してきて、見えない・見えにくいことで困っている困りごとをこのベッドサイトに来て、熱心に話しかけてくれる方達に聞いてもらえて、そのリハの専門家が、見えない・見えにくいことについての基礎知識を持っていて、何か少しでも理解を示したら、工夫出来ることのヒントを与えられたら、きっと見えない・見えにくい状態で、困っている方達は、少しずつ心を開くのではないかと思いました。(私が身体的なリハで私の気持ちを聞いていただいたように)
疾患で見えない・見えにくい状態になった直後の方も、そして既に見えない・見えにくいことでの困りごとを抱えて入院してくる方も、その悩み事を聞いていただいて、理解を示してもらえたら、それは、すごく違うと思った次第です。
だからこそ、病院で働くリハや看護や介護の方達にも、眼科以外の病棟でも、見えない・見えにくい状態になる方達の見え方の知識や、ケアの知識を持ってほしいと強く思いました。
以下雑誌本体の内容です。
月刊視覚障害2025年7月号.pdfをダウンロード
テキスト文章ここから
■■■
Opinion
病院から始まる視覚リハの重要性
~緊急入院を体験して気づいたこと~
視覚障害リハビリテーション協会
吉野 由美子
はじめに
私は現在77歳、先天性白内障によるロービジョン(弱視)と、大腿骨が内側に曲がってしまうという障害をもち、電動車いすで一人暮らしをしています。大学で社会福祉を学び、1974年に就職した名古屋ライトハウスあけの星声の図書館では、在職中の2年間に、人生の半ばで中途視覚障害になった方延べ50名ほどから相談を受けました。その中で、当時ようやく我が国に導入され始めた歩行訓練を中心とした視覚障害リハビリテーション(以下、視覚リハ)の存在と有用性を知り、その普及を私のライフワークにしようと決めて、50年近く活動を続けてきました。
普及活動を始めた頃は、「見えなくなったら何もできない」というのが社会一般の常識でしたし、視覚リハの訓練施設があることも知られていませんでした。そのため、入院しても支援する側も患者自身も手の打ちようがなく、何年にも亘って無為な入院生活を送っている方に出会いました。「視覚リハ自体の有用性が知られれば社会一般の意識が変わる」と当時の私は考え、その日が一日でも早く訪れることを願っていました。
活動を始めて約50年経って、私は緊急入院しました。身体的なリハが入院直後から行われ、その効果を実感すると同時に、視覚リハは未だに行われていない現況を「これはおかしい」と痛感しました。
本稿では、私の体験を通して、入院(受傷)から始まる視覚リハの重要性と他のリハ職と連携して行うリハの必要性とその意義について書いていきたいと思います。
1.緊急入院と翌日から始まった理学療法士によるリハ
(1)重症筋無力症で緊急入院
2023年11月ごろから、ちょっと体を動かすと呼吸が苦しくなったり頻脈が続いたり、まぶたが勝手に下がってきて眼を開けていられないようになりました。原因が分からないまま症状が重くなり、脳神経内科専門医に診てもらって重症筋無力症(注1)という難病であることが判明。直ちに脳神経内科病棟に緊急入院となりました。
この重症筋無力症という病気は、何らかの理由で自分の体を護るはずの抗体が、自分の呼吸などを司る筋肉を敵とみなして攻撃する難病で、治療としては、ステロイドの大量投与と血漿交換などがあります。血漿交換を行うためには、血液の凝固を防ぐための注射をしなければならず、その副作用で、血が止まらなくなり、ほんの少しぶつかったり、指で押したりするだけでも出血してしまうので、何をするにも看護師さんや介護の方が付き添うという状態でした。
(2)脳神経内科病棟の様子
入院している患者は、高次脳機能障害の後遺症と内臓疾患、認知症と内臓疾患など、重度の身体障害と内臓疾患を併せ持ち、多種多様な症状の方が30名ほどいました。
看護の体制は、一人の患者を担当看護師とその助手をする立場の看護師2名で担当、日中と夜間で交代するシステムでした。介護のほうは、入浴やトイレ介助などを行う介護スタッフが担当し、こちらも昼夜交代制でした。一人の看護師が担当する患者数は7名ほどということでした。脳の疾患に関連して精神不安定な症状の患者も多く、スタッフはその対応に追われていました。私への対応の最中に担当している他の患者に何かあれば、看護師はそちらへ行って長時間戻ってこないこともありました。このような状況でしたので、本当は何種類もある薬の形などを手で触ったり、じっくりと目で見たりして確認したかったのですが、早く飲むように促されていました。
看護師が行っていた相対的医行為は、毎食後の血糖値検査(血糖値が高い場合はインスリンの注射)、血液検査、血漿交換等の治療をスムーズに行うための血液をサラサラにする注射を1日2回、毎食後の薬の投与など多岐にわたっていました。それに加えて、前述のとおり出血しやすい状態だったため、ベッドを離れるときは誰かが見守るといった状況で、看護師も介護のスタッフもてんてこ舞いの様子でした。
私のように、血液の凝固を防ぐ注射をうちながら電動車いすを利用している患者の経験がなかったためか、入院当初、病院側から病棟で使用している一般の車いすをスタッフが押して移動する方法を提案されました。私は使い慣れた電動車いすで、自分でできることはやりたいという思いでしたが、私の安全というだけでなく、「もし他の患者さんにぶつけてしまったら」という他者への安全についても、スタッフは不安を持っているのだと感じました。安全第一に多忙なスタッフがやりやすい方法で進めることについては、致し方のないことかと思います。
(3)入院翌日から始まる治療としてのリハ
入院の翌日、理学療法士(PT)が来てリハが開始されました。1日目は、まず、私の体調や身体状況を確認するために、ベッドから起き上がったり立ち上がったり、電動車いすへの移乗などの動作確認をしました。その後、「電動車いすを自操してトイレなどにも一人で行きたい」など、入院生活中に行いたい希望を聞いてくれました。
2日目からは、介護スタッフ付き添いの下、リハビリ室に移動してのリハ。1日1回、移動を含めて40分程度で毎日行われました。最初は、私の靴がきちんとフィットしているかの確認からスタート。それから、ベッドに寝て筋力トレーニング、杖をついての歩行、階段昇降などを行いました。また、私の希望に沿って、一人で安全に電動車いすを用いて移動できるかを確認してくれました。理学療法士の方は私の状況を把握し、専門家として一人で安全にできると判断した項目を病棟のスタッフに伝えてくれました。この対応に私は信頼と自信をもち、一人でできることが増えていきました。(注2)
2.病院から始まるリハの有用性と効果
(1)患者に寄り添う細やかな配慮
リハの基本的理念は、患者の身体的、精神的な自立度を高めることだと私は考えてきました。今回の私のケースでは、転んだり、ぶつけたりして大出血を起こすと命の危険がありましたから、厳しい行動制限がありました。その中で、リハ担当者は「病室で何に困っていますか?」、「何ができるようになりたいですか?」と私に尋ね、希望を実現するために、専門家としての知識を駆使して、筋力を回復させるトレーニングを行ったり、体の動かし方のちょっとしたコツなどを教えてくれたりしました。同時に、安全に一人でできることが増えるような環境改善、例えばベッドの位置や手すりの位置の調整などを、私に合わせて工夫してくれました。これらにより、「こうやればできる」、「ここまでならできる」と実感することができ、次のステップへと進む勇気が湧いてきました。
(2)患者とスタッフの架け橋に
私のリハ担当者として、病棟のカンファレンスなどに出て、その時の病棟の体制も熟知している立場として、無理のない範囲で、スタッフが私の行動をサポートできるように、病棟のチームの一員としてアドバイスし、私にもそのことを伝えてくれていました。患者の口から「私はこれができる、あれをやりたい」と言っても、なかなか思いどおりにはなりませんが、専門家からの「お墨付き」ですので、その後は許可が出るようになりました。
(3)退院後のケアについて適切なアドバイスができる
退院後、訪問リハやデイサービスなど、どのようなタイプの看護・介護を受けるのが良いか、私の身体能力を踏まえた上での助言をしてくれました。これができたのは、病院だけではなく福祉施設などにも拡がっているリハ専門職のネットワークを通して、各施設の状況を把握しているからだと思いました。
3.視覚リハがおかれている状況
理学療法士(PT)や作業療法士(OT)などが行うリハは、外科的な分野だけでなく、脳梗塞などの重度の患者にも有用であることを多くの診療科の医師が理解し、その導入と、リハを担う専門家の育成と国家資格化を促進して発展してきました。そのため、治療の一環として医療保険が適用され、病院等で行われたのです。
一方、視覚障害に対するリハは、治療の見込みのない失明者を対象とし、職業訓練の前段階として歩行や日常生活訓練を行うことを目的として、福祉分野で導入されました。従って、そこで蓄積された専門知識や技術についての有用性は、眼科医を含めた医療の領域にも一般にも知られることなく、評価もされなかったのです。
このようにして、「視覚リハ」は、リハビリテーションの教科書などでもほとんど取り上げられないような、リハ分野から抜け落ちた存在となってしまったのです。
4.病院における視覚リハの必要性
突然視界が失われたり、見えにくい状態で入院する患者は、環境の急変と激しいショックにより、心身ともに大きな負担を強いられます。入院直後に視覚リハの専門知識を持つスタッフが、患者の不安に寄り添い、励ましながらリハビリを始めることは、患者が前向きに次の一歩を踏み出すための大きな支えとなるのです。しかし、病院現場では、内科、外科、整形外科など急性期治療が必要な診療科においても、視覚障害に配慮したケアの知識が乏しく、専門の視覚リハスタッフが配置されていないため、多くの患者が十分な支援を受けられていません。
また、現代の超高齢社会においては、中途で見えにくさや視覚障害を発症する患者が増加しており、その背景には眼の疾患だけでなく、脳梗塞や脳腫瘍手術など、脳の視覚情報処理に関わる問題が存在しています。これに加えて、身体的な麻痺や運動障害など、複合的な問題を抱えるケースも多く、従来の身体的リハビリテーションだけでは対応が難しくなっているのが現状です。
病院でのリハ専門家が理学療法や作業療法を通じたリハビリテーション体制を築いている。一方、視覚リハの専門家は福祉領域に限定され、医療機関での対応は非常に限られているため、患者は「見えない=何もできない」という固定観念に陥りがちです。
この状況を打開するためには、視覚リハ専門家と身体リハ専門家が互いに知識や技術を共有し、連携を深めることが不可欠です。入院時から視覚リハを開始することで、患者に安心感と自立への希望を与え、医療システム全体の中で視覚リハを体系的な支援として組み込む必要があります。実際、初期段階での適切なケアが、患者のリハビリ成功の鍵となるため、病院内での視覚障害に対する理解や指導体制の構築は急務と言えるでしょう。
おわりに
未来に向け、医療現場での視覚リハ専門家の配置や、歩行訓練士会など各関係団体との連携を通じた実践的な方法論の確立が求められています。視覚リハの充実は、単なる情報障害への対処に留まらず、複合的な身体障害や精神的ショックを抱える患者に対して、包括的かつ柔軟な支援体制を提供することで、現代の多様なニーズに応えていく大きな一歩となるのです。
【参考サイト】
(注1)MG ユナイテッド https://mg-united.jp/aboutmg/what-is-myasthenia-gravis.html#toc-2
(注2)吉野由美子の考えていること、していること https://yoshino-yumiko.net